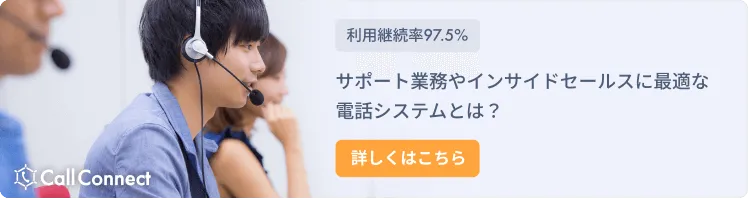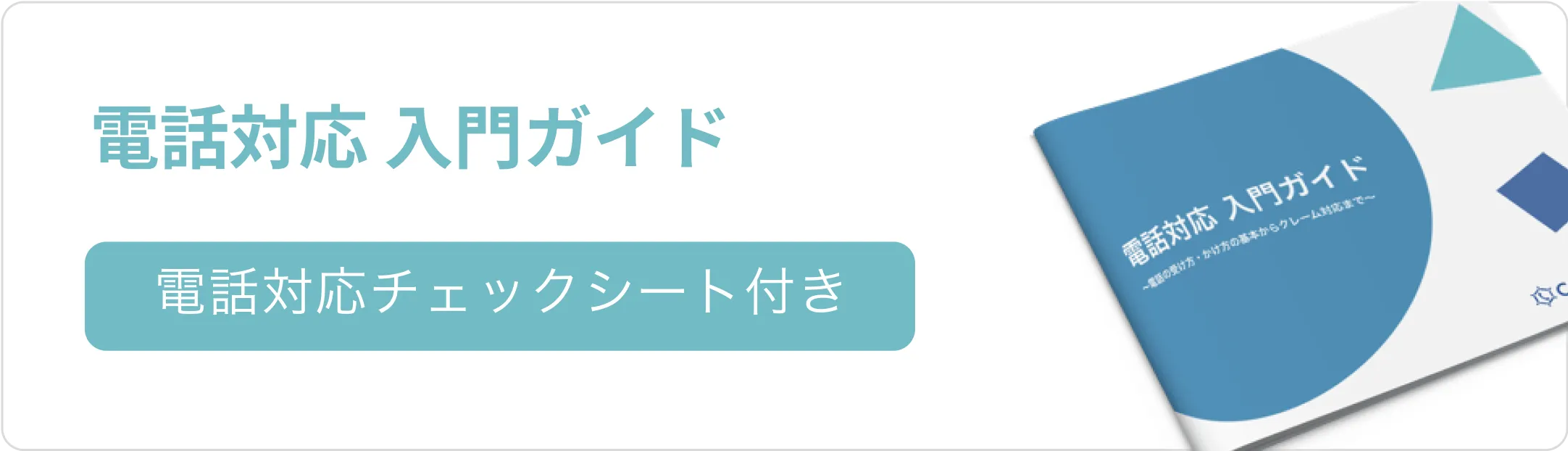こんにちは。「CallConnect」ライターチームです。
コールセンターはお客様との直接的な接点になり、企業のブランドイメージ向上の重要な役割を担います。
しかし、日本では人口そのものが減少し続け、労働人口が減少しているため、コールセンターの高い応答率を維持するために、未経験者であっても採用せざるを得ないケースが出てきます。
では、未経験者に対して基本的な言葉遣いや敬語の正しい使い方を教えるにはどうすればいいのでしょうか?
頭では理解していても、いざ教えるとなると、中々言葉が出てこないものです。
この記事では、コールセンターでよく使われる敬語や実践的な言い回し、間違えやすい敬語や役立つテクニックをご紹介いたします。また、応答時から終話までの一連の流れに沿った、基本的な言葉遣いをまとめました。
敬語の基礎研修資料としても使える一覧表をご用意いたしましたので是非ご活用ください。
- コールセンターで使われる敬語の特徴
- 3種類の敬語
- 敬語は第一印象を左右する
- それはダメ!避けたい言い回し
- 間違えやすい二重敬語
- コールセンターで使用を避けたい用語
- 便利な言葉遣い2選
- 応対の流れに沿った言葉遣い
- まとめ
関連記事:新人オペレーターの離職率を下げる5つの指導法とは?
関連記事:コールセンターの研修の進め方。 押さえるべきポイントは?
コールセンターで使われる敬語の特徴
インバウンドのコールセンターで使われる敬語とアウトバウンドで使われる敬語にはそれぞれ特徴があります。
アウトバウンドのコールセンターでは、お客様との距離感を縮めるため、意図的にややフランクな丁寧語を使うこともあります。
改まった敬語ばかり使っていては、中々親近感を持っていただけないためです。
そのため、敬語の中でも、より日常的に使われる丁寧語を使う頻度が多いのです。
一方、インバウンドのコールセンターでは、企業の代表としての丁寧な対応が求められるため、適切な言葉遣いが重視され、比較的尊敬語を使う機会が多いといえます。
3種類の敬語
敬語は主に3種類あり、丁寧語、謙譲語、尊敬語に分けることができます。
それぞれ下記に解説いたします。
丁寧語
丁寧語は、基本的に「ですます調」の丁寧な言葉遣いのことです。丁寧な言い回しをすることで相手を敬い、一般的にも日常的によく使われる敬語です。
尊敬語
尊敬語は、目上の方への敬意を表す敬語です。「〇〇様が仰る通りでございます」など、丁寧語と違うのは、話題にしている方や、話の相手に関わるものごとや動作について述べる時に使うということです。「御社」、「ご担当者様」など、相手を指す語も尊敬語に分類されます。
謙譲語
謙譲語は、自分や自分が属する組織などについてへりくだって表現することにより、相手を敬う敬語です。「お調べいたします」、「弊社の営業担当の者が参ります」というように、主語は自分や身内、自分が属する組織の人になります。
謙譲語や尊敬語を多用すると、仰々しく感じ、違和感を覚えるお客様もいます。「敬語は使わなくていいよ」と言ってくださる場合もあります。
そのような時は丁寧語を使うことで、お客様に相応しい敬意を示しつつ、会話するのが良いでしょう。
敬語は第一印象を左右する
コールセンターでは声だけを頼りに対応を進めていきます。表情など、お客様の反応が読みにくいのは、対応の難易度を上げる要素となります。
しかし、それはお客様にとっても同じです。対面の接客では見た目の印象が重要ですが、コールセンターでは、オペレーターの声や言葉遣いが判断材料になります。
ちょっとした言葉遣いやニュアンスの違いで、お客様を不快にさせてしまう可能性もあるのです。
ですから、もし敬語を使えないとすればジャージ姿で法人営業に行くようなものであり、受付を突破することすらできないでしょう。
適切な敬語を使えるかどうかはコールセンターの接客においても非常に重要であり、第一印象を左右します。
また、声の調子や高さも印象に影響しますので、普段話す声よりもワントーン高く、明るくハキハキ話すことにより、より一層好印象を与えることができるでしょう。
|
21パターンの敬語比較一覧 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
通常 |
丁寧語 |
謙譲語 |
尊敬語 |
|
|
1. |
する |
します |
いたす |
なさる |
|
2. |
言う |
言います |
申す、申し上げる |
仰る |
|
3. |
見る |
見ます |
拝見する |
ご覧になる |
|
4. |
読む |
読みます |
拝読する |
お読みになる |
|
5. |
聞く |
聞きます |
伺う、お聞きする |
お聞きになる |
|
6. |
尋ねる |
尋ねます |
伺う |
お尋ねになる |
|
7. |
書く |
書きます |
お書きする |
お書きになる |
|
8. |
行く |
行きます |
参る、伺う |
いらっしゃる |
|
9. |
来る |
来ます |
参る、伺う |
いらっしゃる お越しになる |
|
10. |
帰る |
帰ります |
おいとまする |
お帰りになる 帰られる |
|
11. |
会う |
会います |
お目にかかる |
お会いになる 会われる |
|
12. |
いる |
います |
おる |
いらっしゃる |
|
13. |
待つ |
待ちます |
お待ちする |
お待ちになる お待ちくださる |
|
14. |
送る 送付する |
送ります 発送します |
送らせていただく ご送付いたします |
ご発送いただく お送りになる |
|
15. |
受け取る |
受け取ります |
頂戴する たまわる |
お受け取りになる |
|
16. |
伝える |
伝えます |
申し伝える |
お伝えになる |
|
17. |
知る |
知っています |
存じ上げる(人) 存じる(物) |
ご存知 お知りになる |
|
18. |
わかる |
わかります |
かしこまる 承知する |
おわかりになる ご理解ただく |
|
19. |
考える |
考えます |
検討いたします |
お考えになる ご高察なさる |
|
20. |
思う |
思います |
存じる 拝察する |
お思いになる おぼしめす |
|
21. |
利用する |
利用します |
利用させて いただく |
ご利用になる |
それはダメ!避けたい言い回し
お客様の声が聞こえない時
突然お客様の声が聞こえなくなると、つい「聞こえますか?」と言ってしまいそうになりますが、この言い方は「お客様の聴力などに問題がある」と言っているような印象を与えかねないため、「私の声は届いておりますでしょうか?」と言い換えましょう。
お客様が納得されない時
「ですから、先ほども申し上げましたが~」
お客様が何度も同じことを主張してくると、こう言いたくもなりますが、「くどい」と言っているようなものです。
そもそも、お客様がそう仰る原因は、「自分の言っていることをわかってほしい」、あるいは「担当者がわかってくれない」と感じているからです。
しかし、「~ということでございますね。お客様の仰る通りでございます。私にできる最善の提案は~でございますがいかがでしょうか?」
と、答えるならば随分印象が変わってきます。
まずお客様の気持ちに共感し、受け止めて、代替案を提案すると、お客様は気持ちをやわらげて、応じてくれやすくなるでしょう。
こちらから書類を送付する時
「お客様がお送り頂く形となります」という言い回しもよく聞きますが、送っていただくことに”形”は特にありませんので、シンプルに「送って頂けますか」で問題ありません。
保留中のやり取りにも注意
エスカレーションのために手上げをして、状況を報告することはよくありますが、普段からSVに、「クレームです。めっちゃ怒ってます。」等と伝えるのはやめておきましょう。
なぜなら、保留を押したつもりでも、実際に保留になっていないケースが時折見受けられるからです。実際に、このことが原因で、さらなるクレームに発展する場合があるのです。
また、「保留になっていれば何を話してもいい」という訳ではありません。隣で話しているオペレーターのマイクが、そのやり取りを拾ってしまい、お客様が気分を害したり、企業そのものへの印象を損ねてしまったりすることもあるからです。
たとえクレーム対応であっても、日頃からお客様を敬う気持ちを忘れないようにしましょう。
|
避けたい言い回し |
相応しい言い回し |
|---|---|
|
わかりません。 |
申し訳ございませんがわかりかねます。 |
|
なるほど |
左様でございますか |
|
そうですね |
左様でございますね |
|
書類の方ご返送いただけますか |
書類をご返送頂けますか |
関連記事:コールセンターのクレーム対応のコツ
間違えやすい二重敬語
丁寧に話そうと思うあまり、敬語を重ねて使ってしまうと過剰な敬語=二重敬語になってしまう場合があります。
|
二重敬語 |
正しい敬語 |
|---|---|
|
お尋ねさせていただいてもよろしいですか? |
お尋ねしてもよろしいですか? |
|
ご確認させていただきましたところ |
確認いたしましたところ |
|
拝見させていただきましたところ |
拝見したところ |
|
拝見いたします |
拝見します |
|
お帰りになられる |
お帰りになる |
|
仰られる通りです |
仰る通りです |
コールセンターで使用を避けたい用語
たとえ社内では普通に使っていても、コールセンターでは避けるべき用語や言葉遣いがあります。それぞれ詳細を解説します。
社内用語
社内用語とは、「キャリア」など、会社内で独自に使用している用語のことで、社員同士のような共通の認識がなければ理解できないものです。お客様に対して理解できない言葉を使うべきではありません。
専門用語
専門用語とは、「PBX」など、業界内でしか通じない用語や、特定の分野に精通していないと理解できない用語のことです。意味を取り違えてしまいかねない用語もありますし、こちらも同様にお客様に対して理解できない言葉を使うべきではありません。
ファミコン言葉
ファミコン言葉とは、コンビニエンスストアやファミリーレストランで使われる間違った言い回しのことです。ファミレス言葉、コンビニ言葉ともいわれます。
例えば、ファミリーレストランで「ご注文はハンバーグ定食でよろしかったでしょうか?」というような言い回しをよく聞きます。
意味は伝わりますが、これでは、「お客様は、この瞬間までハンバーグ定食を食べたかったんですね。でも今は?本当にファイナルアンサー?」と尋ねているようなものです。
今何を注文したいかを聞いているのに、過去形に言い換えるのは不自然ですので、この言い回しはプロとして避ける必要があります。
正しくは「よろしいでしょうか」です。
また、過去形で表現してしまうのは、営業活動を行うアウトバウンドのコールセンターでも見受けられますが、避けた方が良いでしょう。
参考:【シーン別】コールセンターで使ってはいけないNGワード20選
便利な言葉遣い2選
クッション言葉
クッション言葉とは、ストレートに伝えるとキツイ印象を与えてしまうような言葉の衝撃を、クッションのようにやわらげてくれる言葉のことです。また、言いにくいことを伝えなければいけない状況で、自分自身の心の負担を軽減する効果もあります。
結論から先に話すことで応対時間を短くすることができますが、その一方で、ご要望に沿えない時などに唐突に結論を言ってしまうと、事務的で冷たい印象を与えてしまいます。
ご要望の結果だけでなく、対応についても不満を与えてしまいかねませんので、下記のようなケースではもれなく使用しましょう。
|
利用シーン |
クッション言葉の例 |
|---|---|
|
オールマイティ |
恐れ入りますが |
|
何らかの作業をお願いする時 |
お手数ですが |
|
やや立ち入った質問をする時 |
失礼ですが |
|
不便を強いる状況 |
ご不便をおかけしますが |
|
要望に沿えない時 |
ご要望に添えず申し訳ありませんが 心苦しいのですが |
|
迷惑をかける時 |
ご迷惑をおかけいたしますが |
|
質問する時等 |
差し支えなければ もしよろしければ |
Yes・but話法
Yes・but話法とは、相手の意見を肯定した後に、逆説として自分の意見や代替となる提案を述べるトークスキルです。
すぐに相手の意見に反論してしまうと、こちらの意見も聞いてくれなくなる恐れがありますが、まず自分から相手の意見を一旦受け止める姿勢を見せることで、相手も耳を傾けてくれるようになります。
例えば、お客様が購入を迷っている理由を話してくださった時などに、巧みな営業トークを織り交ぜると、決断を後押しすることもできるのです。
これはビジネスシーンだけでなく、日常生活でも円滑なコミュニケーションに役立ちます。
応対の流れに沿った言葉遣い
コールセンターでは、応答時から終話時までの一連の流れに沿った、基本的な言葉遣いがあります。
特に謝罪に関しては、具体的に謝ることで、お客様の気持ちをやわらげやすくなるので、バリエーション豊かに習得しておきましょう。
|
シチュエーション |
トーク例 |
|---|---|
|
電話を受ける時 |
お電話ありがとうございます、 (社名+名前)でございます。 大変お待たせいたしました(待ち時間が長い場合) |
|
電話をかける時 |
お世話になっております。 |
|
質問する時 |
失礼ですが、〇〇様との続柄を教えて頂けますか |
|
保留する時 |
30秒ほどお待ち頂けますでしょうか |
|
保留を解除する時 |
お待たせいたしました |
|
ご要望を伺った時 |
かしこまりました |
|
依頼する時 |
お手数ですが、書類をご返送頂けますでしょうか |
|
感謝する時 |
貴重なご意見ありがとうございます |
|
謝罪する時 |
お急ぎのところ申し訳ございません ご心配をお掛けして申し訳ございません ご不便をお掛けして申し訳ございません |
|
不明点確認 |
他に何かご不明な点はございませんでしょうか |
|
終話時の名乗り |
本日は私(名前)がご案内いたしました |
|
終了挨拶 |
今後とも(社名)をよろしくお願いいたします お電話ありがとうございました |
まとめ
今回の記事では、敬語の基本的な使い方をご紹介しました。
敬語を話すのは、社会人としてはもちろん、コールセンターでは必須のマナーです。適切な敬語を使い分けることでブランドイメージと顧客満足度を高める対応ができるでしょう。
「電話対応 入門ガイド」は、基本的な電話の受け方やかけ方、クレーム対応の流れについて解説した無料ガイドです。
「電話対応の基本的な流れがわからない。」「新人スタッフに何から教えればいいのかわからない。」という方は、ぜひ資料をダウンロードの上、電話対応の品質向上にお役立てください。