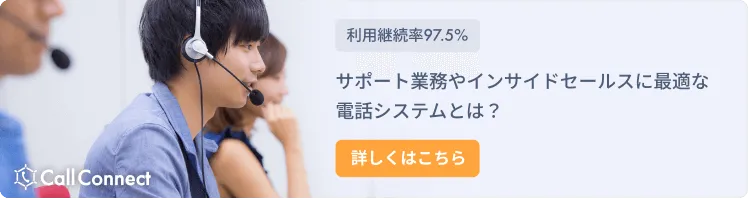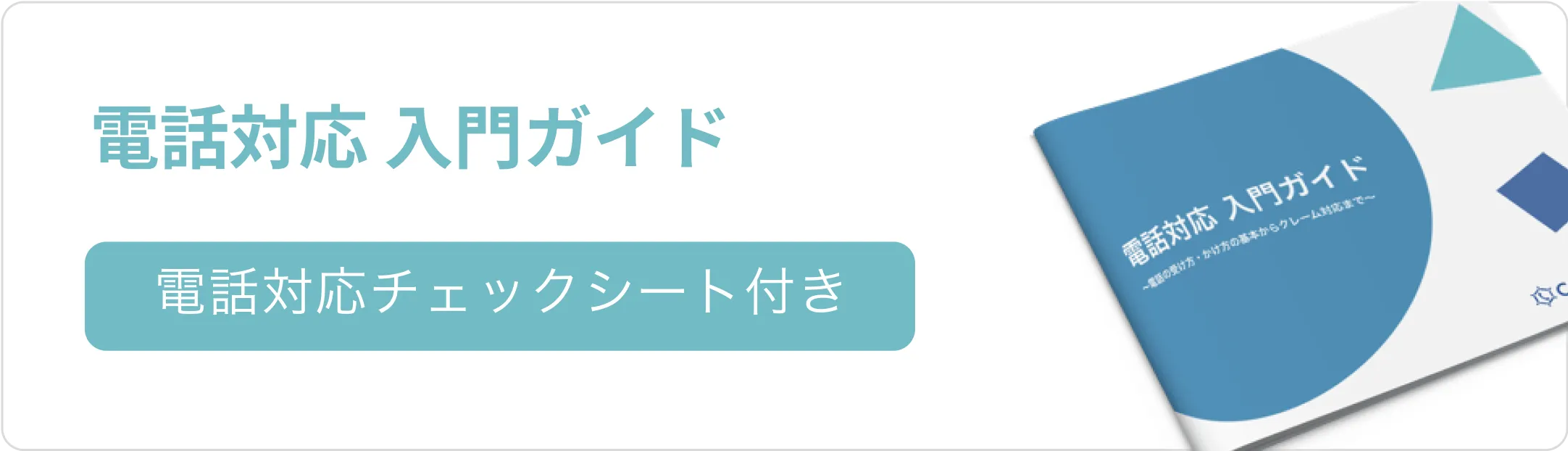少子高齢化や人手不足を背景に、「シニア雇用」を拡大する企業が増えています。一方で、シニア層の採用に漠然とした不安を抱いている管理者の方も少なくないようです。
大前提として、求人を出す際に年齢を制限することは、雇用対策法で禁じられています。書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為も、法の規定違反。事業者は、年齢に関わらず、すべての人に均等な機会を与えなければないのです。
そこで本記事では、シニア雇用の概況やコールセンターにおけるシニア雇用の注意点などについて解説していきましょう。
シニア雇用とは
シニア雇用とは、一般的に60歳以上の人材を雇用することを指します。
総務省の労働力調査によると、60代以上の就業者数は2023年時点で1,468万人。就業者全体に占める比率は21.8%で、調査開始以来最高値を更新しました。下図の通り、20〜34歳までの就業割合である23.2%に肉薄する勢いです。

シニア層も「人生100年時代」を意識し、長く働き続けたいと考えている人が増えています。内閣府が発表した「令和6年版高齢社会白書」によると、現在収入のある仕事をしている60歳以上の人のうち、「働けるうちはいつまでも」働きたいと回答した者が約4割。「70歳くらいまで」または「それ以上」との回答と合計すれば、約9割が高齢期にも高い就業意欲を持っている様子がうかがえます。
一方で、60歳以降に「給与に不満がある」という理由で転職する人が増加傾向にある点も見逃せません。

日本経済においてシニアが貴重な戦力となる中、企業にはシニア就業者の待遇向上や就労環境の整備が欠かせないのです。
65歳までの雇用確保(義務)と70歳までの就業確保(努力義務)
シニア雇用の増加傾向には、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」も少なからず影響しているでしょう。
2021年(令和3年)4月1日に改正されて以来、高齢者の雇用について以下のようなルールが設けられています。
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、以下いずれかの措置を実施する必要がある。
①65歳までの定年の引上げ
②希望者全員を対象とする、65歳までの継続雇用制度を導入
③定年の廃止
<70歳までの就業確保の努力義務>
定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講ずるよう努める必要がある。
①70歳までの定年の引き上げ
②希望者全員を対象とする、70歳までの継続雇用制度を導入
③希望者全員を対象とする、70歳までの業務委託契約制度を導入
④70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度を導入
⑤定年の廃止
少子高齢化が継続する以上は、将来的に「70歳までの雇用確保」も義務化される可能性が高いと考えられます。現在、65歳までの雇用は確保できている企業であっても、70歳雇用に向けた対策を検討しておくと良いでしょう。
![]()
65歳以上への定年引上げや高年齢の有期契約労働者の無期雇用へ転換を行う事業主には、「65歳超雇用推進助成金」が給付される可能性があります。
詳細は、以下サイトにてご確認ください。
▶65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省
シニア層がコールセンターで活躍する理由
シニア雇用の機運が高まる中、コールセンターは以下のような理由からシニア層が活躍しやすい職場と言えます。
- 働きやすい環境
- 豊富な社会経験
- 同年代からの問い合わせに有利
働きやすい環境
コールセンターは以下のような理由から、シニア層も働きやすい環境と言えます。
・座り仕事で体力をあまり必要としない
・シフト制で勤務時間の融通がきく
・小売業、旅行業、金融業など様々な業種の募集がある
こうした条件が揃っているからこそ、未経験の方でも活躍しやすいのです。
豊富な社会経験
コミュニケーション能力が重視されるコールセンターでは、経験値の高いシニア層が活躍できる場面が多くあります。特に、問い合わせを受けるインバウンドのコールセンターでは、年齢を重ねたことによる”思慮分別”や”落ち着き”が顧客に安心感を与え、信頼を得やすいです。
インバウンドの特徴をより詳しく知りたい方は、是非以下の記事もご一読ください。
また、2024年に株式会社LIFULLが行った調査によると、シニア層の採用を行っている企業のうち「採用した65歳以上の人材が即戦力であったことがある」と回答したのは、約7割。シニア層の経験やスキルは、大いにポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。
同年代からの問い合わせに有利
下図の通り、コールセンターの利用者、つまり「電話で問い合わせする顧客」の年齢層は、年々高齢化しています。ご年配のお客様に対し、共感しながら親身な対応ができるのは、シニア層の強みです。

コールセンタージャパン・ドットコム | 2023年5月号 <第2特集>
若者には話しづらい内容でも、同じシニア層のオペレーターには安心して質問できる、という方は意外と多いもの。
こうした背景から、保険、化粧品、健康食品といったジャンルでは、顧客の年齢層と合わせたミドルシニアやシニア層の採用を積極的に行う企業が増えています。
コールセンターのシニア雇用における注意点
コールセンターがシニア層を雇用する際に、気を付けるべきなのは以下3点です。
- 他のメンバーと分け隔てなく接する
- 健康面の配慮が不可欠
- 自発的な転職者は増加傾向
他のメンバーと分け隔てなく接する
シニア雇用をすると、上司の方が年下になるケースが多いです。その際、年上部下とその他のメンバーであからさまに態度を変えるのはやめましょう。
2023年のパーソル総合研究所の調べによると、シニア就業者のうち「年下の上司のもとで働くことに抵抗はない」割合は、過去最高の55.4%。一方、シニア向けのアンケートの中で「腫れもの扱いされるのが嫌だ」「困ったときに質問できる人がいない」といった意見が挙がっているのも事実です。
基本的に、シニア層だからといって特別扱いをする必要はありません。むしろ、すべてのメンバーに対して以下のようなポイントを常日頃から気をつけるようにしましょう。
・挨拶する
・敬語を使う
・頭ごなしに否定しない
・他の人と比較しない
・質問しやすい雰囲気をつくる
健康面の配慮が不可欠
シニア雇用において、「長時間の勤務は避ける」などの配慮は不可欠です。年齢とともにトイレが近くなり、若いオペレーター以上に頻繁な休憩が必要という方もいます。
しかし、高齢だからといって「注意力が落ちるだろう」「パソコン操作も苦手なはず」といった先入観をもつべきではありません。年齢別にオペレーターの後処理時間を調査した某コールセンターでは、「在籍期間が短い20代」よりも「在籍期間の長い50代以降」の方が後処理時間が短いという結果も出ています。
従業員の健康面に配慮し、長く働き続けられる環境を整えることで、ノウハウを蓄えたシニア層の活躍が期待できるのです。
自発的な転職者は増加傾向
先述の通り、給与に不満を抱いて転職するシニア就業者は増加傾向にあります。
2022年の厚生労働省の調査結果では、60代以降の就業者の18.2%が転職を経験し、他の年代の就業者と比較すると、30代の就業者に次いで高い水準でした。つまり、「シニア層は転職しづらいから辞めないはず」といった固定観念は、もはや通用しません。常により良い条件の職場を求めているのは、どの年代も同じなのです。
すでにシニア雇用を行っている企業では、シニア従業員の定着やさらなる活躍を期待して、報酬や処遇を見直しつつあります。尚、60歳以降に賃金が低下した従業員には、65歳までの雇用継続を支援する目的で、国から「高年齢雇用継続給付金」が支給される可能性があります。以下のサイトで詳細をチェックしておきましょう。
▶雇用継続給付について|厚生労働省
まとめ
近年では、AIや自動化ツールの活用により、コールセンターの様々な作業が自動化されています。そのため、シニア層にとっても業務負担は軽くなりつつあると言えるでしょう。
「技術の進化」と「シニア層の豊富な経験」の融合により、コールセンターがより発展することを期待したいですね。
<関連記事>コールセンターに有人対応は必要か?AIとの使い分けについて解説 - CallCenter Times(コールセンタータイムズ)
「CallConnect」は、クラウド型のコールセンターシステムです。
シンプルなインターフェースのため、老若男女問わず手軽にご利用いただけます。「コールセンターシステムを手軽に導入したい」という方は、無料トライアルをお試しください。