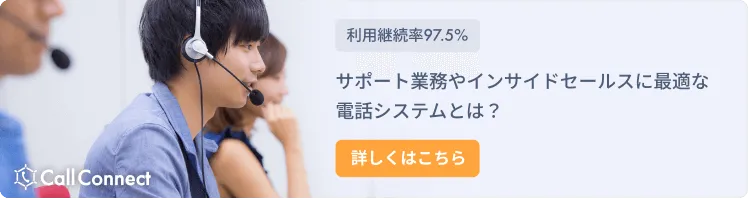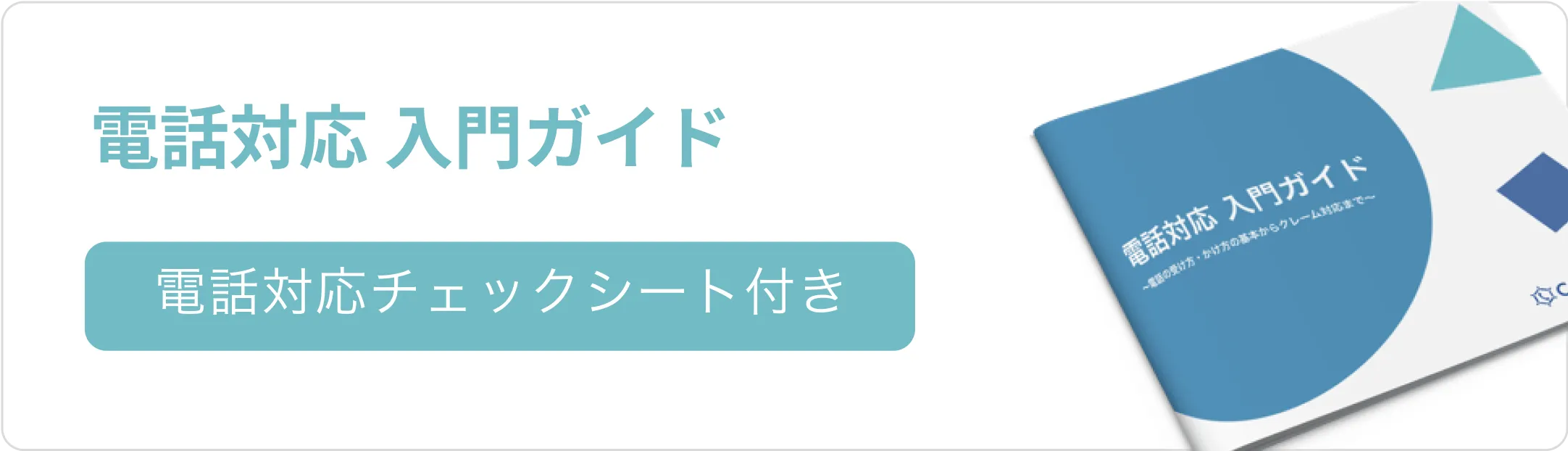コールセンターの業務で発生しがちな事柄として、「担当者がいない(不在)」があります。
担当者がたまたま休日だった、病欠で出勤していない、会議中で対応できないなど、その理由はさまざまでしょう。
では、担当者不在時に顧客から指名で入電があった場合、コールセンターとしてどのような対応が望ましいのでしょうか?
今回は、担当者が不在でも適切な対応ができるよう「顧客情報の共有方法」について解説します。
顧客情報をきちんと共有できていないことで発生するデメリットについても説明しますので、リスクヘッジの観点からもしっかりと理解しておきましょう。
- そもそも担当者指名の入電があること自体が珍しい
- 担当者不在時に実践すべき正しい電話対応の方法
- 担当者不在に備え顧客情報を共有する方法は主にこの2つ
- 顧客情報の共有ができていないことで発生する2つのデメリット
- 【例文紹介】担当者不在時は不在理由によって顧客への回答が変わる
- まとめ:顧客情報の事前共有でより良いコールセンターが実現できる
そもそも担当者指名の入電があること自体が珍しい
大前提として、コールセンターで担当者を指名した入電があること自体が珍しいです。
というのも、コールセンターでは、担当窓口のオペレーターであれば、全員が同レベルの対応ができるようトレーニングされているため、指名制を採用する必要がないのです。
では、なぜ担当者を指名した電話が入るのでしょうか?その理由として考えられるのは以下の2つです。
① 以前から継続して対応している案件
② 担当オペレーターの対応に顧客が満足したから
それぞれ内容を解説します。
① 以前から継続して対応している案件
以前から継続的に対応している案件であれば、担当者を指名したうえで入電があるケースも考えられます。
例として、クレーム対応をオペレーターではなく管理者が担当するセンターも存在します。その場合であれば、担当の管理者を指名した入電があっても珍しくありません。
② 担当オペレーターの対応に顧客が満足したから
過去に担当したオペレーターの対応に顧客が満足していると、まれに指名で電話が入るケースがあります。
とはいえ、先述したようにコールセンターでは、基本的に指名制を採用していないため、大抵の場合は最初に受電したオペレーターが対応を継続する流れが一般的です。
担当者不在時に実践すべき正しい電話対応の方法
担当者不在時に顧客から指名で入電があった場合は、以下の流れで話を進めるとスムーズに対応できます。
- 担当者が不在である旨を説明
- 代わりに対応できることがないか確認
- 担当者からの折り返し架電を提案
最初にすべきことは「1.担当者が不在である旨を説明」です。このときの第一声は謝罪から入り、「大変申し訳ございません。〇〇(担当者)は〇〇(不在の理由)で休みを取っております」と不在である旨をしっかりと相手に伝えます。
そのあと、応対履歴の閲覧や管理者からの指示を聞いたうえで、「2. 代わりに対応できることがないか」確認してください。この際、クレーム案件のようなイレギュラー対応であれば、オペレーターが無理に引き受ける必要はありません。後日担当者に対応してもらうか、管理者に対応をゆだねてください。
代わりに対応できることがないとわかった場合は、最後のステップとして「3.担当者からの折り返し架電を提案」します。この際、オペレーターの独断で提案するのはリスクが高いため、必ず管理者の指示のもと対応してください。
担当者不在に備え顧客情報を共有する方法は主にこの2つ
コールセンターにおいて、担当者不在に備えた顧客情報の共有方法は主にこの2つです。
① 登録されている顧客情報を参照する
② 管理者間の連絡網で情報を共有しておく
どのような内容かみていきましょう。
① 登録されている顧客情報を参照する
コールセンターでは、専用のシステムに顧客情報を登録しています。登録されている情報には、前回の対応履歴(折衝履歴)も含まれており、そこには「いつ・誰が・どのような内容で対応したのか」が記録されています。
そのため、顧客から入電があった際はシステム上の履歴を確認し、それをもとに対応します。
システムによっては重要事項を入力する欄が通常の履歴登録欄と別に設けられているケースもあるため、情報の見落としが発生しないよう注意が必要です。
② 管理者間の連絡網で情報を共有しておく
コールセンターの多くは、管理者だけがやり取りできる連絡網を整備しています。
筆者がコールセンターで管理者をしていた頃は、Excelを連絡帳として活用していました。
このような連絡網に、いつ・どのような問い合わせがあったのかを共有しておくだけで、急に顧客から連絡がきても慌てずに対応できます。
顧客情報の共有ができていないことで発生する2つのデメリット
顧客情報の共有がしっかりできていないと、以下の2つのデメリットが発生します。
① 顧客情報の確認に時間がかかる
② 重クレームに発展する恐れがある
これらはとくに重要なのでしっかり理解しておきましょう。
① 顧客情報の確認に時間がかかる
顧客情報の共有がしっかりされていないと、入電時の情報確認に余計な時間を要します。そうなると、課題解決までにかかる時間も増加するため、顧客に過度なストレスをあたえます。
顧客満足度の低下にも直結するため、顧客情報を共有する際はシステム上に履歴を詳細に残すなど、いつでも引き継ぎ対応が可能な状態にしておかなければなりません。
② 重クレームに発展する恐れがある
クレームにかかわる案件で顧客から入電があった際、顧客情報がきちんと共有されていないと重クレームに発展する恐れがあります。
重クレームの解決には多くの時間と労力を必要とします。場合によっては、SVなど現場の管理者レベルでは解決できない事態を招く可能性もあります。
そうなるとコールセンター全体の評判も悪くなってしまうため、顧客情報の事前共有はとても重要です。
【例文紹介】担当者不在時は不在理由によって顧客への回答が変わる
担当者不在時の不在理由によって顧客への回答は変化します。いくつか例をあげてご紹介しますので、実際にそのような場面があった際は活用してください。
■担当者が“休み”の場合
「申し訳ございません。本日〇〇(担当者)は休みを取っております。よろしければ私が代わりにご対応してもよろしいでしょうか?」
■担当者が“別件対応中”の場合
「申し訳ございません。〇〇(担当者)は別件対応中でございます。終わり次第こちらから折り返しのご連絡をしてもよろしいでしょうか?」
■担当者が“休憩中”の場合
「申し訳ございません。現在〇〇(担当者)は席を外しております。戻りましたらこちらからご連絡してもよろしいでしょうか?」
■担当者が“退社”したあとの場合
「申し訳ございません。〇〇(担当者)は本日すでに退社しております。明日は〇時から出社しておりますので、明日あらためてご連絡してもよろしいでしょうか?」
【注意ポイント】
先述したように、指名入電はクレームなどイレギュラー対応中の案件である可能性が極めて高いです。そのため、管理者に対応方法を確認したうえで顧客対応を行いましょう。
まとめ:顧客情報の事前共有でより良いコールセンターが実現できる
質の高いコールセンターの実現には、顧客情報の事前共有が必要不可欠です。
共有不足によるトラブルが発生しないためにも、システム上での詳細な記録や管理者間の情報共有を徹底してください。
顧客により満足してもらえるコールセンターになるためにも、情報共有の重要性を忘れないようにしましょう。
「CallConnect」は、情報共有に最適なコールセンターシステムです。
着信時に過去のやりとりを見ながら顧客対応ができます。「顧客情報を共有してスムーズに電話対応したい」という方は、無料トライアルをお試しください。